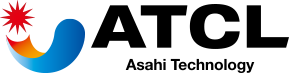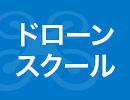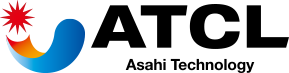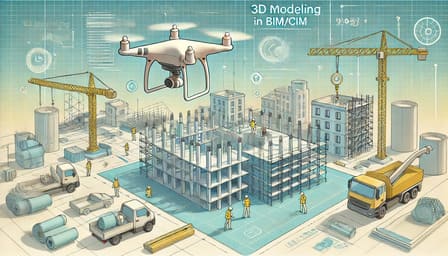
建設業界におけるBIM/CIMの原則適用が進む中、ドローン技術の活用が不可欠となっています。本記事では、ドローンがもたらす効率化と精度向上について、具体的な事例を交えながら解説します。
目次
BIM/CIMとは?基本と原則適用
BIM/CIMの基本概念
BIM(Building InformationModeling)とは、建物のライフサイクル全体を通して、3次元モデルを中心に、設計、施工、維持管理の情報を一元化する概念です。一方、CIM(ConstructionInformationModeling)は、土木構造物を対象とした同様の概念で、道路、橋梁、トンネルなどのインフラプロジェクトに適用されます。BIMとCIMは、それぞれの分野における情報共有と連携を強化し、プロジェクトの効率化と品質向上を目指します。両者の違いとしては、対象とする構造物が建築物か土木構造物かという点があります。しかし、共通の目的は、情報の一元化と可視化を通じて、プロジェクト関係者間のコミュニケーションを円滑にすることです。また、設計段階から完成後の維持管理まで、一貫したデータ活用を可能にすることで、手戻りの削減やコスト削減に貢献します。
令和5年度からの原則適用
国土交通省は、令和5年度から公共事業におけるBIM/CIMの原則適用を開始しました。これは、建設業界全体の生産性向上と効率化を目的としたものであり、全ての公共工事において、BIM/CIMの導入が求められるようになります。この原則適用により、従来の2次元図面中心の業務プロセスから、3次元モデルを活用したプロセスへと大きく転換することが期待されています。これにより、設計段階での干渉チェックやシミュレーションが容易になり、施工段階での手戻りやミスを大幅に削減できます。また、維持管理段階においても、3次元モデルを活用することで、効率的な点検や修繕計画が可能になります。さらに、情報共有の円滑化により、関係者間の連携がより強化されます。原則適用は、建設業界全体にとって大きな変革をもたらすものと考えられます。
適用範囲と対象業務
BIM/CIMの適用範囲は、設計、施工、維持管理の各段階に及びます。具体的には、企画、基本設計、実施設計、施工計画、施工、維持管理、更新など、建設プロジェクトのライフサイクル全体をカバーします。対象となる工事の種類は、建築物だけでなく、道路、橋梁、トンネル、河川、港湾などの土木構造物も含まれます。義務項目としては、3次元モデルの作成、属性情報の付与、情報共有基盤の活用などが挙げられます。一方、推奨項目としては、4D(時間軸)シミュレーションや5D(コスト)管理などが挙げられます。これらの項目は、プロジェクトの規模や特性に応じて適用が検討されます。BIM/CIMの導入にあたっては、プロジェクトの目的や要件を明確にし、適切な適用範囲と対象業務を定めることが重要です。また、関係者間の合意形成を図りながら、段階的に導入を進めることが望ましいです。
ドローンによる3次元モデル作成と活用
ドローン測量のメリット
ドローン測量は、従来の地上測量と比較して、大幅な時間短縮とコスト削減を実現できます。広範囲の地形や構造物を迅速かつ安全に測量できる点が大きなメリットです。また、ドローンに搭載された高精度カメラやセンサーにより、高解像度の3次元モデルを効率的に作成できます。これにより、従来の測量では困難だった場所や、危険な場所での測量も安全に行うことが可能です。さらに、ドローン測量で取得したデータは、BIM/CIMモデルとの連携が容易であり、設計、施工、維持管理の各段階で活用できます。具体的なメリットとしては、測量時間の短縮、測量コストの削減、高精度なデータ取得、安全性の向上などが挙げられます。特に、広大な土地や複雑な地形の測量においては、ドローン測量のメリットが最大限に発揮されます。
3次元モデルの活用事例
ドローンで作成した3次元モデルは、建設現場において様々な用途で活用されています。例えば、設計段階では、地形データの把握や、構造物の配置検討に利用されます。施工段階では、進捗管理や出来形管理に活用され、実際の現場とモデルとの差異を比較することで、施工の品質管理に役立ちます。また、災害発生時には、被災状況の把握や復旧計画の策定に利用されることがあります。さらに、維持管理段階では、構造物の劣化状況の把握や、点検計画の策定に活用されています。具体的な事例としては、造成工事における土量計算、橋梁の点検、道路の舗装状況の把握などが挙げられます。これらの事例からわかるように、3次元モデルは、建設プロジェクトの各段階において、効率的な作業と品質向上に貢献しています。また、3次元モデルを活用することで、プロジェクト関係者間のコミュニケーションが円滑になり、情報共有がより効果的に行われます。
データ共有と連携
ドローンで取得したデータは、クラウドプラットフォームやデータ共有システムを通じて、他の関係者と容易に共有できます。これにより、設計者、施工管理者、発注者など、プロジェクトに関わる全ての関係者が、常に最新の情報を共有し、連携を取りながら業務を進めることができます。DS(Data-Sharing)の重要性は、プロジェクトの透明性と効率性を向上させるために不可欠です。データ共有の際には、セキュリティ対策を講じることが重要であり、アクセス権限の設定や暗号化などの対策が求められます。また、データ形式の標準化も、データ連携をスムーズに行うためには重要です。オープンデータ形式を採用することで、異なるソフトウェア間でのデータ互換性を確保できます。データ共有と連携を適切に行うことで、建設プロジェクト全体の効率性と品質が向上します。
先進企業に学ぶBIM/CIM導入のポイント
福留開発株式会社の事例
福留開発株式会社は、BIM/CIMの導入において、先駆的な取り組みを行っている企業の1つです。同社は、まず自社の業務プロセスを徹底的に分析し、BIM/CIMを導入する目的を明確化しました。その上で、パイロットプロジェクトを通じて、BIM/CIMの効果を検証し、課題を洗い出しました。次に、社員向けの研修プログラムを整備し、BIM/CIMに関する知識と技術の向上を図りました。さらに、3次元モデル作成のための機材を導入し、内製化を進めました。また、社内における情報共有体制を構築し、BIM/CIMの導入効果を最大化しました。同社の事例からわかるように、BIM/CIMの導入は、単にソフトウェアを導入するだけでなく、業務プロセスや組織体制の見直しも必要となります。また、社員への教育や技術支援も重要な要素となります。
内製化とマニュアル作成
BIM/CIMを効果的に活用するためには、内製化を進めることが重要です。内製化とは、自社でBIM/CIMモデルを作成し、自社でデータ分析や管理を行う体制を構築することを意味します。内製化を進めるにあたっては、まず、専門知識を持った人材を育成する必要があります。また、3次元モデルを作成するためのツールや機材を導入し、環境を整備する必要があります。さらに、社員向けの教育プログラムを設け、技術向上を図る必要があります。内製化を円滑に進めるためには、マニュアル作成が不可欠です。マニュアルには、BIM/CIMの基本操作から、3次元モデル作成の手順、データ管理の方法まで、詳細に記載する必要があります。また、定期的にマニュアルを見直し、最新の情報に更新する必要があります。内製化を進めることで、外部委託コストを削減できるだけでなく、自社の技術力向上にも繋がります。
人材育成と教育支援
BIM/CIMを効果的に活用するためには、専門知識と技術を持った人材の育成が不可欠です。人材育成は、社員研修、外部セミナーへの参加、資格取得支援など、様々な方法で行われます。教育支援としては、研修プログラムの作成、講師の派遣、教材の提供などが挙げられます。また、大学や専門学校などの教育機関と連携し、BIM/CIMに関する教育プログラムを共同で開発することも有効です。人材育成においては、技術的な知識だけでなく、BIM/CIMを導入する目的やメリットを理解させることが重要です。また、最新の技術動向を常に把握し、自己研鑽に励む意識を持たせる必要があります。さらに、チームでの情報共有や連携を促し、組織全体としてBIM/CIMの活用能力を高める必要があります。継続的な教育支援により、BIM/CIMの活用能力を高めることが、建設業界全体の発展に繋がります。
ドローンを活用した教育と地域連携
府中東高等学校での取り組み
広島県立府中東高等学校では、ドローンを活用したBIM/CIM授業を積極的に展開しています。この授業では、ドローン測量の基礎知識や操作方法を学び、実際の建設現場を3次元モデル化する実習を行います。生徒たちは、ドローンを操作するだけでなく、取得したデータを解析し、BIM/CIMモデルを作成するスキルを習得します。この取り組みは、次世代の建設技術者を育成するだけでなく、地域社会への貢献も目指しています。学校と地域企業が連携することで、生徒たちが実際の建設現場で活かせる知識や技術を習得できる点が特徴です。また、地域企業にとっては、将来の優秀な人材を確保する機会にもなります。府中東高等学校の取り組みは、ドローン技術を活用した教育の可能性を示しており、他地域への波及効果も期待されます。
課外授業と資格取得
ドローンに関する課外授業は、生徒たちの興味や関心を高め、より専門的な知識や技術を習得する機会を提供します。課外授業では、ドローンの飛行技術だけでなく、測量技術やデータ解析技術、BIM/CIMモデル作成技術など、幅広い分野を学びます。また、ドローンに関する資格取得を支援することで、生徒たちの進路選択の幅を広げることが期待されます。資格取得に向けた取り組みとしては、資格試験対策講座の開講や、模擬試験の実施などが挙げられます。これらの取り組みを通じて、生徒たちはドローンに関する専門知識を習得し、将来のキャリア形成に繋げることができます。また、課外授業や資格取得支援を通じて、生徒たちの学習意欲を高め、主体的な学習態度を育むことができます。ドローン技術を習得することで、社会に貢献できる人材育成を目指しています。
地域発展への貢献
ドローン技術を活用した教育は、地域発展に大きく貢献します。ドローン技術は、建設分野だけでなく、農業、防災、物流など、様々な分野で活用されており、地域産業の活性化に繋がる可能性があります。また、ドローン技術に関する人材育成を進めることで、地域に新たな雇用を創出することも期待できます。さらに、地域住民向けのドローン講習会を開催することで、地域全体のドローンに対する理解を深めることができます。地域住民がドローン技術を習得することで、地域課題の解決に繋がる新しいアイデアや事業が生まれる可能性も高まります。このように、ドローン技術を活用した教育は、地域産業の活性化、雇用創出、地域課題の解決に貢献し、地域全体の持続的な発展に繋がります。地域連携を強化することで、より大きな効果を生み出すことができるでしょう。
まとめ
BIM/CIM原則適用におけるドローン活用の将来性
本記事では、BIM/CIMの基本概念、原則適用、ドローンによる3次元モデル作成と活用、先進企業の事例、教育現場での取り組みについて解説しました。令和5年度からのBIM/CIM原則適用により、建設業界は大きな変革期を迎えています。ドローン技術は、BIM/CIMを効果的に活用するための重要なツールであり、建設現場の効率化や生産性向上に大きく貢献します。また、人材育成や教育支援は、BIM/CIMをより普及させるために不可欠です。特に、ドローン技術を活用した教育は、次世代の建設技術者を育成するだけでなく、地域発展にも大きく貢献することが期待されます。今後、BIM/CIMとドローン技術の連携はますます強化され、建設業界のデジタル化が加速すると考えられます。その中で、最新技術を積極的に取り入れ、人材育成を進める企業が、競争力を高めていくでしょう。
私たち、旭テクノロジーは10年近いドローン運用のノウハウと、多くの企業への導入支援・社会実装を通じて培った実績があります。ドローン測量で取得した3次元データは、CIMソフトに連携することで、CIMモデルの作成に活用することができ、現況地形を正確に再現したCIMモデルを作成することができます。ドローンとCIMソフトを連携させて、業務を効率化してみませんか?今すぐ問い合わせる⇒