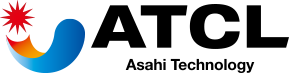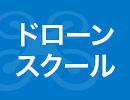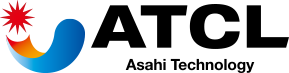ドローンの資格取得や事業には費用がかかります。ドローンの資格取得において、どのような支援を受けられるのかを知りたい人も多いでしょう。この記事では、個人事業主も使用できる、ドローン事業で受けられる助成金や補助金の種類、注意点などを解説します。ドローンの導入や資格取得を目指している人は、ぜひ参考にしてください。
ドローンの資格取得に受けられる助成金
ドローンの資格取得に受けられる助成金には、さまざまな種類があります。それぞれの助成金について解説します。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の受給条件は以下のとおりです。
- 人材育成訓練:OFF-JT(職場外研修)を10時間以上行った場合
- 認定実習併用職業訓練:中核人材育成のために実施するOJTと、OFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合
- 有期実習型訓練:正社員への転換を目的に実施するOJTと、OFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合
有期実習型訓練を除き、雇用形態を問わず訓練の受講ができます。ただし、詳細については頻繁に改正が行われており、申請時は厚生労働省の該当ページを確認することが重要です。
働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金は、企業を支援する助成金であり、働き方の改善や従業員の労働環境の改善を目指します。以下の条件に該当する中小企業事業主が対象です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主である
- 交付申請時点で、「成果目標」の設定に向けた条件を満たしている
- 交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備している
参考:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|厚生労働省
農林水産業における助成制度
農林水産業におけるドローンの活用が急拡大するなか、農林水産業に限定した助成制度があります。どのような制度があるのかを解説します。
経営継続補助金
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を、回復させる取り組みを支援する補助金です。1人でも作業可能な農薬散布用ドローンを導入するような、感染拡大防止対策を併用できる場合に向いています。採択率が高く、特にドローン導入の採択例が多いことが特徴です。
強い農業・担い手づくり総合支援交付金
農産地に必要な農業用機械の導入支援が目的です。農業支援サービスの事業主が対象となり、農業用ドローンの取得やリースなどの費用に対して受給できます。農業経営や経営基盤の発展を目指しています。
参考:令和5年度強い農業づくり総合支援交付金のうち農業支援サービス事業支援タイプの公募について|農林水産省
産地生産基盤パワーアップ事業
収益強化に取り組む産地に対して、総合的に支援する事業のため、ドローン導入が該当する場合は対象となります。「強い農業づくり総合支援交付金」と異なる点は、産地の農業者が一体となった集団的な取り組みを重視していることです。全国産地の土づくり支援も行っています。
ドローン事業で受けられる補助金
設備投資や研究、ソフトウェア開発などドローン事業において受けられる補助金を解説します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営計画に基づいた販路開拓のための補助金で、最大250万円が交付されます。採択率は30~90%であり、平均60%と幅が広いことが特徴です。公募は通年受け付けているため、1度審査に落ちても再度応募が可能です。個人事業主も対象となり、比較的審査に通りやすいといわれています。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、ドローン事業における設備投資や部品製造、サービス開発などを担う事業者に対する補助金です。採択率は50%前後と他の補助金と比べて、高くありません。補助額は、業種や規模などによりますが、特例を併用すれば5,000万円が上限となります。
IT導入補助金
IT導入補助金は、ドローンを飛ばすソフトウェアやアプリなどの、ITツールを導入に使用できる補助金です。補助上限額は5~450万円となっており、補助対象のソフトウェアが指定されているため、応募時に判断しやすいことが特徴です。指定外のソフトウェアを導入する場合は利用できないので、事前確認が必須です。
ドローンの助成金・補助金を受けるまでの手順
ドローンの助成金・補助金を受けるまでには、さまざまな手順を踏まなければなりません。その過程を解説します。
個人・企業に合った助成金・補助金・助成金を探す
個人事業主であれば自分に、企業担当者であれば会社に合った助成金や補助金を探す必要があります。必要であれば、専門家に相談することも方法の1つです。
各都道府県労働局に申請する
必要書類を提出する際は、1か月前までに完成させましょう。誤字脱字や書類不備などがないかを確認することがポイントです。書類は、都道府県労働局に提出します。
審査を受ける
基本的な審査の流れは、資格審査、書類審査、面接審査の順序で進みます。面接審査は、事前にきちんと対策しておくとよいでしょう。
採択が決定する
審査に合格することで、助成金や補助金が交付される権利を得られます。報告書提出後、事業実施が確認されると費用が支給されます。
助成金・補助金を受ける際の注意点
助成金や補助金を受ける際には、さまざまな注意点があります。それらを確認し、審査に通るための対策に役立ててください。
後払いが基本
助成金や補助金は基本的に後払いのため、立て替える必要があります。たとえば、250万円の事業の場合は、先に自社や自分で250万円を支出することになります。補助額を差し引いた資金を用意するのではなく、事前に必要な資金の把握が重要です。
対象期間はそれぞれの制度によって異なり、厳密に決まっています。資金の調達が難しい場合は、交付されるまで、つなぎ融資を受けることもよいでしょう。
条件や期限が厳しく手間がかかる
助成金や補助金は、不正受給の防止や公平な審査のため、条件や期限は厳しくなっています。
助成金や補助金を受けられた場合は、国から要件を満たしていると認められたことになり、社会的信用が高まります。申請手続きは、事業ごとに異なるため、各種申請書や添付資料などをそろえる必要があります。
正確な事務処理が求められる
事業実施終了後は、期間内に計画書や報告書を提出しなければなりません。書類不備や目的以外の支出などがあると、支払いを拒否されるケースもあります。会計検査院の調査対象になる可能性もあるため、確実な事務・会計処理が求められます。規定に沿い、適切に進めましょう。
100%受けられる制度ではない
申請しても、助成金や補助金は必ず支給されるとは限りません。厳しい審査を通過する必要があります。審査が通っても、書類不備があったり不透明な事項があったりすると、支給されないケースも見られます。ただし、審査が通れば確実に受給できるため、対象期間の確認や書類の準備など、審査通過に向けてできることを行いましょう。
まとめ
ドローンの導入における補助金や助成金制度は、条件や制度によって異なり、金額や補助率もさまざまです。自社や自分に合ったものを見定めて、申請有無を検討してください。受給を希望する際は、要件や期限が厳しい場合もあるため、注意点を考慮しながら早めに準備をすることが重要です。
株式会社旭テクノロジー(ATCL)は自社事業にドローンを活用しつつ、スクールでは、ドローンの操縦に関する指導を行っています。国土交通省の認定登録講習機関として、7年で2000人以上の卒業生を排出した実績もあります。無料体験会を実施しているため、興味のある人は、ぜひお問い合わせください。